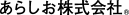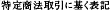塩を農業に活用!~塩で野菜が甘くなる。農産物の質を向上させる使い方
2025/03/29

塩を、農業に活用できることをご存じですか?皆さんは、「塩トマト」を食べたことがあるでしょうか。干拓地など、塩分の残る土壌で育った、甘みの濃い、おいしいトマトです。「塩は作物に悪影響を与える」というのが一般的な認識ですが、 実は、適量の塩を上手に活用することで、農作物の味や質を向上させることが可能です。沿岸部で育つ農作物は、他の地域に比べて美味しいと言われることが多く、その理由の一つに「塩の影響」があります。
適切な方法で塩を使えば、農薬や化学肥料を減らしつつ、健康で美味しい作物を育てることができます。本記事では、塩を農業に取り入れるメリットや具体的な方法について解説します。
1. 塩がもたらす農作物へのメリット
適量の塩が植物に与えられると、光合成の促進やストレス耐性の向上にもつながります。例えば、適度な塩ストレスを与えることで、作物が自らの防御機能を高め、病害に強くなることが知られています。塩が作物に与える好影響には、以下のようなことがあるといわれています。
1.植物の浸透圧調整と耐ストレス性向上
適量の塩分は植物の浸透圧を調整し、水分の吸収や保持を助けることがあります。特に乾燥環境では、適度な塩分が根圏の水分を保持し、植物の水分ストレスを軽減する効果が期待できます。
適応応答の活性化
植物は低濃度の塩ストレスにさらされると、浸透圧調整物質(プロリン、ベタイン、糖類など)を合成し、細胞内の水分を保持しやすくなります。
この結果、水分の少ない環境でも生育できたり、水分をしっかり蓄えた作物が収穫できます。
2.ミネラル供給による成長促進
塩は、ミネラルの代表格です。
塩=塩化ナトリウムには、ナトリウム(Na)と塩素(Cl)が含まれており、これらの成分が特定の作物の成長を促すことがあります。
ナトリウム(Na)の役割
①ナトリウム(Na)の利用
ナトリウムは、一部の植物(トウモロコシ、ビート、ほうれん草など)で、カリウム(K⁺)の代わりとして機能することがあります。カリウムは植物にとってとても重要な栄養素ですが、ナトリウムが少しあればカリウムの使用量を減らせるため、植物の成長を助けることがあります。
② 光合成を助ける
ナトリウムは、光合成で使われる「葉緑体」の中で、水分やイオンのバランスを整える役割をします。特にナトリウムをうまく活用できる植物では、光合成の効率が少し良くなることがあります。
③ 乾燥に強くなる(水分保持)
ナトリウムが適量あると、植物が水をうまく保持しやすくなり、乾燥に強くなることがあります。これは、ナトリウムが水を引き寄せる性質を持っているためです。
塩素(Cl)の役割
塩(塩化ナトリウム)に含まれる塩素イオン(Cl⁻)は、植物にとって大切な栄養素のひとつです。適量であれば、植物の成長を助けるいくつかの良い影響があります。
①光合成の促進
植物が太陽の光を使ってエネルギーを作る「光合成」では、水を分解して酸素を出す大切な反応があります。このとき、塩素イオンは水の分解をスムーズに進め、光合成の効率を上げる役割をします。そのため、適量の塩素イオンがあると、植物は元気に成長できます。
② 水分の調節をサポート
植物の葉には「気孔(きこう)」という小さな穴があり、ここから水を蒸発させたり、空気中の二酸化炭素を取り込んだりしています。塩素イオンは、この気孔の開け閉めを調整する働きをし、植物が乾燥しすぎないようにサポートしてくれます。特に暑い日や乾燥した環境では、この働きがとても大切です。
③ 病気に強くなる
塩素イオンには、カビや細菌の増殖を抑える効果があります。植物の根や葉を守り、病気になりにくくすることで、元気な状態を保つのに役立ちます。
④ 一部の作物の成長を促す
トウモロコシやサトウキビのような特定の作物は、塩素イオンを上手に活用して成長します。適量の塩素イオンがあると、これらの作物はより早く、健康に育ちます。
3土壌病原菌の抑制
一部の病原菌は高い塩分環境では生育しにくくなります。例えば、
フザリウム菌(萎ちょう病の原因)
ピシウム菌(根腐れ病の原因)
これらの菌は塩分耐性が低く、軽度の塩ストレスを利用して病害を抑えることが可能です。
害虫忌避効果
一部の害虫は塩分濃度の高い環境を嫌うため、塩の施用によって害虫被害が減少する場合があります。
4.果実の品質向上
植物が一定量の塩分にさらされることで受ける影響のことを塩ストレスといいます。塩濃度が高すぎると浸透圧の変化により根の水分吸収が阻害され、成長に悪影響を与えます。しかし、適度な塩ストレスを与えることで、作物は適応しようとし、糖分やアミノ酸を増やしながら成長するため、結果的に味が向上することがあります。適度な塩ストレスを加えることで、果実の糖度や旨味が向上することが知られています。
ブドウ、トマト、スイカなどの作物では
軽い塩ストレスを与えることで水分の吸収が抑えられ、果実の糖濃度が上昇する。
カリウムとナトリウムのバランスが変化し、風味や食味が良くなる。など。
香り成分の増加
一部の野菜では、ストレス応答により特定の香り成分(リコピンやアントシアニンなど)が増加することが報告されています。
2. 沿岸部の事例:塩の効果が自然に現れる環境
塩の効果を理解する上で、沿岸部の農業に注目してみましょう。千葉県や瀬戸内地域など、海に近いエリアでは、潮風や海水の影響を受けながら作物が育ちます。これらの地域で収穫される作物は味が濃く、甘みが増していることが特徴です。
熊本県の元々塩田だった土地や干拓地で栽培されているトマトは、土壌に塩分が残っていることから、冒頭にも書いた「塩トマト」と言って、味が濃厚でおいしい高級品とされています。
また、昔から海水を活用した伝統農法が存在しており、一部の地域では今も実践されています。これは、塩分が適度に含まれることで作物の成長が促進される事例の一つです。
沖縄では、海水を適度に希釈し、サトウキビや野菜に散布することで病害を抑え、ミネラルを補給する農法が行われています。佐渡では、塩分を含む地下水を活用し、米の品質向上に役立てる方法が伝統的に続けられていて、米の粘りや甘みを高める工夫がなされています
また、瀬戸内地域では、潮風に含まれる塩分がミカンの糖度を向上させることが知られており、海に近い段々畑での栽培が盛んです。
みかんの産地は静岡県・和歌山県など海に面しているところが多くあります。静岡市久能の石垣いちごも、海岸沿いで塩分を含む風を受ける環境で育つことで甘く濃厚な味わいになると言われています。
3. 具体的な塩の活用方法
土壌に塩を適量施用
土壌改良の一環として、適量の塩をまく方法があります。土壌の通気性・保水力の向上が期待できます。
作物が根から塩分を吸収し、塩ストレスを与えられることでより強く、より良い味を引き出します。
ただし、過剰に使用すると塩害を引き起こす可能性があるため、適切な量を見極めることが重要です。
海水を希釈して葉面散布
海水を適度に希釈し、葉面散布することでミネラルを直接補給する方法もあります。この際、適正な濃度(一般的には0.1~0.5%程度)を守ることが大切です。
灌漑水に塩
米の栽培においては、海水を適量混ぜた灌漑水を使用することで食味が向上する事例が報告されています。
作物によって塩の影響は異なります。例えば、トマトやスイカは塩ストレスにより甘みが増しますが、塩に弱い作物もあるため、作物ごとに適した方法を選ぶ必要があります。
4. 適用の際の注意点
塩を農業に活用する際は、以下の点に注意する必要があります。
適量の管理が重要
NaCl濃度が0.1~0.3%程度(1000~3000 ppm)の低濃度であれば、植物の生理機能に良い影響を与える場合がある。
0.5%以上になると多くの作物に塩害が発生するため、慎重な管理が必要。
カリウムとのバランスを考慮
カリウム(K)は植物の成長に重要な要素であり、ナトリウムが過剰になるとカリウムの吸収が阻害される可能性があるため、適切な施肥バランスが必要。
土壌の塩分蓄積を防ぐ
連続して塩を施用すると、土壌に塩が蓄積し、作物の生育を阻害するリスクがある。
適宜、灌漑(かんがい)を行い、余分な塩を流す対策が重要。
使用量はEC値(土壌や水の中の電気の通りやすさを表す数値)を使って適切な管理を
塩の具体的な使用量は、作物の種類、土壌の性質、気候条件など多くの要因に左右されるため、一概に数値を示すことは難しいです。そのため、土壌のEC値を定期的に測定し、適正な範囲内に維持することが重要です。ECメーターを使用して土壌の塩類濃度を測定し、その値を参考に使う塩の量や施肥量を調整することが推奨されています。
5. まとめ:塩を賢く使い、持続可能な農業へ
塩は適量なら作物の質を向上させる強力なツールです。沿岸部の事例から学び、適切な方法で活用することで、農薬や化学肥料に頼るだけでなく、健康で美味しい作物を育てることが可能です。
塩を賢く取り入れることで、持続可能な農業を実現し、消費者に安全で高品質な農産物を届けましょう。
世界自然遺産に指定された清浄な海域の天日塩を原料とし、伝統的な平釜直火製法で丁寧に作られた「あらしお」は、結晶の良さから、大変溶けやすいため作業性がよく海水中の様々なミネラルを自然に残しています。詳しくは公式サイトをご覧ください。